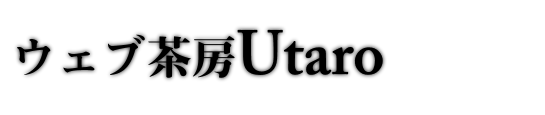![]()
健次が、吉男のアパートに連れられたのは、それが初めてであった。吉男の恋人の幸子が、手料理を拵えて待っていると言われたので、健次は断る理由を見つけられぬまま、吉男の車でアパートに向かったのである。
健次が車から降りると、頭上から幸子の華奢な声が聞こえた。
「健次さんいらっしゃい」
健次はその方を見上げ、二階の窓で笑っている幸子に挨拶をした。吉男は無言でアパートの入り口に入っていったので、健次はその後ろに附いていった。
アパートの入り口に入ると、天井がざらざらとしていて、埃っぽく湿った空気が鼻を突いた。吉男の部屋の郵便受けには、商店街のチラシやらが刺さっていたが、彼はそれに無頓着で、健次もまた、それを吉男に告げようとはしなかった。
ドアを開けると、部屋の中から日本料理風の煮物の匂いがし、そこに幸子の影が見えた。やがて、ぐつぐつと煮えた鍋の音と幸子が箸を揃える音が聞こえ、彼女が目の前に現れた。
「いらっしゃい」
幸子は化粧をしていた。口紅が真っ赤に照り、健次は意味もなく彼女の目線と合わすことをしなかった。吉男はぶっきらぼうに靴を脱いで裸足になると、立ち止まることなく奥の部屋に入っていってしまった。健次は幸子の後を追うようにして、台所に進んだ。台所はひどく狭かった。
「もうすぐ出来るんだけど、味はちょっと自信ないの」
健次は微笑んで見せたが、返事はしなかった。
「ちょっと味見してくれる?」
幸子の話し声は小さくなり、健次の顔を窺った。健次は、差し出された小皿に口を付け、煮物の味見をしてみせた。
「ちょうどいいんじゃないかな」
健次が一言だけ言うと、幸子は、
「そう?じゃあこれでいいわね」
と言いながら、火を止め、盛りつけの支度を始めた。健次は黙って台所を抜け出て、吉男のいる部屋に向かった。
健次が吉男の家にやってきてから、小一時間が経った。幸子の手料理はほぼすべてたいらげており、幸子は満足そうであった。吉男はテレビに夢中で、幸子も片づけを始めだし、健次は何となく手持ちぶさたになった。
「手伝おうか?」
「いいわよ」
会話はそこで途切れ、幸子は台所へ行ってしまった。
部屋には、吉男と健次が残され、健次の手持ちぶさたの度合いがさらに増した。それから数分後、玄関に置いてある電話が鳴り響いた。幸子が出て、応対した。――相手は幸子の母親であった――少しばかり話をし、電話を切ると、幸子はこちらの部屋に入ってきた。
「お母さんから電話だったの。ちょっと実家に行ってきたいんだけど」
吉男はテレビの画面を見つめたまま、
「いいよ。行ってくるといいよ」
幸子は吉男の車を運転し、発進していった。
健次は部屋の隅々を舐めるように眺めた。――この前3人でドライブした、長瀞でのスナップ写真。吉男の趣味のゴルフで稼いだトロフィーと賞状。幸子が吉男にねだって買ってもらったというキャラクターグッズの置物。幸子の脱ぎ捨てたままの靴下、吉男の白いシャツ、灰皿からこぼれ落ちたカーペットの上の吸い殻。どちらかから抜け落ちた髪の毛――。
健次の目は、部屋の隅に置かれていたゴミ箱にまで移った。そこには、先ほど吉男が丸め捨てたタバコの包装紙の下に、何か判然としない物があった。一瞬ではわからなかったが、しげしげと眺めているうちに、それが何であるかわかった。
その物はコンドームであった。結び目を拵えて縛られていた細長い袋。その下部には、はっきりとわかる乳白色の液体が内包されていた。健次は目を瞑ろうと思ったが、結局そうはしなかった。
あの液体は、目の前に座っている吉男である。そしてこのコンドームは、幸子の体内から取り出された物である。健次の想像は、数分前に食べ尽くした煮物に転じていた。ぐつぐつと煮えたまま、鍋の中で全裸の幸子が悶え、踊り狂い、喘ぎ声を上げている。幸子の乳房が大きく揺れ、その中央に液体が流れ落ちる。吉男の精液である。
健次はようやくここで目を瞑った。胸の鼓動が激しくうねり始め、体内が沸騰するかのような熱を感じた。やがて体内の熱は冷めたようだが、今見た視線の先から、もっと鋭く熱い圧迫を感じた。胃の中で消化されつつある煮物の液体が、健次の身体を溶かしていくように思われた。
何故、あのような物を、無造作に捨てているのだろうか。それまで抱いていた幸子に対する律儀なイメージは、瓦解し始め、吉男の鈍感さに対する嫌悪を抱いた。
やがて幸子が帰ってくると、せわしくテーブルの上に買ってきたアイスクリームを差し出した。
「今日はなんだか暑いから、急に食べたくなって買ってきたの」
幸子に勧められた健次は、アイスクリームを一口食べた。そこには堂々とした健次がいた。その最中も、健次は視線をあの方へ移したが、幸子にも吉男にも気づかれなかった。
健次がアパートを出たのは、ほとんどその直後であった。車で送られることを拒否した健次は、徒歩で帰宅した。その途中、健次は何度も何度も呟いた。
《さようなら さようなら…》
――9年後。健次は偶然に、吉男と幸子のあのアパートの前を通りかかった。アパートには誰も住んでおらず、廃墟と化していた。幸子が顔を覗かせたあの二階の窓は、今も形をとどめているが、吉男と幸子があれからどこをどう流浪したのか、健次には皆目見当もつかなかった。にわかに、灰色の空が青色に染まり、健次の額に暖かな光が射した。健次は立ち止まってあの窓をじっと眺め続け、記憶の中の景色と、目の前の実相とを脳裏で重ね合わせ、意外なほどの精確な合致を愉しんだ。
〈了〉
(2001.05)