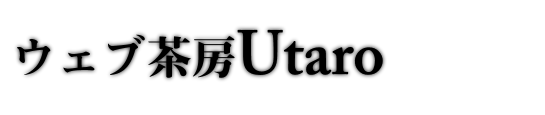![]()
2005年頃、PS2のゲーム『ドラゴンクエスト8 空と海と大地と呪われし姫君』にインスパイアされ、「喫茶Kottoの小さな物語」を書いた。
ちなみに、私のブログ「Kotto Blog」の由来はここにある。
その『ドラゴンクエスト8』のフィールドに、架空の喫茶店をオープンしたという設定の想像の産物である。
ここにそのテクストを残すことにした。
※ゲーム『ドラゴンクエスト8 空と海と大地と呪われし姫君』とは直接関係ありません。
〈第一話〉「風鳴りのエイプリル・フール」
冷たい風が吹き付けるこの地方では、旅人が一時の休息と安らぎを求めるために、小高い山の石窟に身を潜める。
リブルアーチ地方の工芸家(主に彫刻家)たちが、北のオークニスに向かう途上の中継地点として、この「風鳴りの山」の壁面を掘り、山の頂上の見晴らしを堪能したという伝説があるのかないのか、私は知らない。
だが、いずれにしても、このスライム達が棲み着いた険しい山に、人工の隧道や渡り橋があることは事実である。
*
私のカフェ・ショップ「喫茶kotto」は、そんな山の頂にある。
ここから下界を見渡せば、この地方の素晴らしい自然の造形美が一望でき、また旅の進路をも見定めることができよう。
一匹のスライムが、ぴょこぴょこと跳ねながら話しかけてきた。
「ね、ねえ、キミ。この山のてっぺんに住むの?」
「うん」
「この山には、世界中からやってきたスライムたちが遊びに来るの。てっぺんは、ひなたぼっこに使うの。このあたりは風が冷たいから」
「ふーん、そうなんだ。もしかして、僕が山の上に住むのはいけないこと?」
「ううん、それはかまわないんだ」
「君も世界のどこかから、この山に遊びに来たの?」
「最初はそうだったんだけど、今はここのガイド員をしているの。間違って、ライドンの塔に昇ってしまう観光スライム達もいるしね」
(そういえば私は、まだあの塔に一度しか昇っていない。今度落ち着いたら、ライドンの塔に行ってみよう…)
「それでね」
「それで?」
「キミがてっぺんに住むのなら、僕たちは違う場所でひなたぼっこするから、あの場所の貸し代として、毎月必ずひなたぼっこ賃もらいたいの」
「ひなたぼっこ賃?」
「そう、ひなたぼっこ賃」
「というと、ゴールドが欲しいのかい?」
「ううん、ゴールドはいらない。メダルもいらない」
「じゃあ、何が欲しいの?」
「…ヌーク草」
私はぎくりとした。このカフェをやるに当たって、飲料水とほぼ等しく、大量に調達しなければならないのは、ヌーク草であった。そのヌーク草をひなたぼっこ賃にしようというのは、このスライムも抜け目がない。
「うん、ヌーク草だったら、まあ、いいよ」
「ありがとう。毎月、必ずお願いね」
スライムはぴょこぴょこ跳ねながら去っていった。
――毎月、ヌーク草をどれだけひなたぼっこ賃として計上しなければならないのか、あのスライムは何も言わなかった。
では、毎月、売り上げの1%を時価換算して、あのスライムにオークニスから買い付けたヌーク草を納めることにしよう――。
それにしても、あのスライムは、ヌーク草が好物なのか。あるいは何かに利用するつもりなのか。私にはまだ、そのあたりのことが何もわからなかった。
〈第二話〉「一杯のコーヒー」
「一昨年前だったか、右手にキンキラキンの指輪をした、小太りの商人さんがいらしたのですが、昨年の夏、大腸ガンで亡くなりましてな」
オークニスからの帰り道、持病の神経痛がひどくなったので、ちょっと寄っていくことにしたと言っていたその商人は、カウンターに寄りかかるようにして私の顔に近づき、そっと耳打ちしたのだった。
大腸ガンで死んだのは、どこか国の小太りの商人さんで、今それを目の前で話してくれているのは、オークニスから寄り道してきた、大太りの商人さんである。名前は知らない。
彼は、ごくごくと飲み干すコーヒーの味などどうでもいいほど、長い時間、そこに鎮座している。話し好き、と言えば聞こえはいいが、よほど孤独な旅をしてきたのか、まるで何年ぶりかに人と話をした、と想像してしまうほど、彼の口が密閉することはなかったのである。
つまり彼は、今飲んでいるコーヒーには、ガンの発生率を抑える効果があるということを言いたかったらしい。
糖尿病がどうとかという話にもつながったのだが、そういった彼の述べる医学的な見解よりも、その脂ぎった大太りの身体が、いつ糖尿病とやらで不健康に陥るか否かの方が、私には気になって仕方がなかった。
さらに話が、老人介護とバリアフリーの話題に移ったようだが、まったくその頃は、私の両耳は遠い空を向いていた。
孤独。…孤独感。
若い時分には、孤独ということをひたすら考えていたように思う。自分はなんて孤独なんだろう、と。
嫉妬心か何かで他人に憧れる、という些細な気持ちが、いつしか他人になれない自分の孤独に憂いを感じ、何故それが悲哀なのかわからないまま、涙を流したことさえあった。
こんなところでカフェを営んでいる自分は、他人から見れば孤独であるかもしれない。でも孤独ではないと落ち着いて思える気持ちが、今、自分を制御している。それは、充実した日々の何かが、そこに確実にあるからだ。
気がつくと、大太りの商人さんの話は、いつの間にか、地球環境汚濁の話になっていた。
この人はいったいどこでそんなことを考えているのだろう、と心底思った。
〈第三話〉「旅の予感」
私が話を切り出した。
「最近、私は、この世界の魔物について興味があるんです」
客の老人はコーヒーを片手に、応えた。
「ほう、それはまた何かの研究かね?」
「いえ、そんな大袈裟なことではないのですが、例えば、スライムたちは、いったいどこでどのようにして繁殖するのでしょうか?」
すると、なんとも物静かな老人の笑い声が店内に反響した。
「さあ、どこでどのようにして…なんだろうねえ。でもその一方で、スライムベスなどは、絶滅するんじゃないのかね」
「えっ!」
私は素っ頓狂な声を出して驚いたが、老人はいたって冷静であった。
「スライムベスは、スライムの変異種だからね。何故あのように赤くなったのかわからないし、もともと何故スライムは青いのか、その理由もわからない」
私は応えに窮し、俯いてしまった。
「この世界を見渡せば、魔物だけに限らず、あらゆることが謎に満ちているのだよ」
「謎ですか」
「そう、謎だ。…キミは一度、世界を旅したと聞いているが、その謎について、一度でも答えを見つけることができたかね?」
私は確かに、この世界を旅した。大海原を渡り、大地を横断し、闇の世界にも足を踏み入れた。だがそこに多くの謎が点在し、その謎について答えを見つけることなど、いやそれ以前の問題として、問いかけることすらしなかった。
ああ、私はいったい何を旅したのだろう。
何のために旅をしたのだろう。
「そういえば、ここに棲み着いているスライムが、君に話しかけてきたそうだが、そのスライムと、いったい何を話したのかね?」
「ええ。私がここに住むことを伝えましたら、
スライムは、そのかわりにひなたぼっこ賃をくれと」
「ひ、ひなたぼっこ賃!」
一月の売り上げから、1%のひなたぼっこ賃、つまりヌーク草をスライムにくれるという例の取引のことを説明した。そして彼は、小さく溜息をついたようだった。
「うーん。まあ、それはね、君。きわめて魔物的と言わざるを得ないんだよ」
私はしばらく考え込んだが、その文脈の意味が良くわからなかった。
「ま、魔物的?」
「まあ、君もその調子でスライムと仲良くやり給え。ハハハハ」
〈魔物的と言わざるを得ない〉とは、いったいどういう意味だろうか。
確かに私は、旅の途中でこんなことを考えたのだ。パルプンテなどといったたいそうな呪文を研究するより、強力なニフラム呪文があれば、敵を遠くへ――それもこの世界を超えた宇宙へ飛ばせる――そうすれば、この世はきっと争いをしなくなるだろう。少なくともその呪文が、抑止力となるのだから、と。
だがしかし、それを覆すような強靱な魔物が存在するからこそ、私は旅をするのだという矛盾を、理論上克服することはできなかった。
〈最終話〉「有閑マダム」
私はトロデーン城の衛兵から転属し、サヴェッラでの近衛兵の役職に就いたが、しばらくしてその仕事を退いた。
私にとって隣人というべき人たちは、良家であるラグサット家であり、むしろそれは、腐れ縁というべき関係であった。泥酔したラグサットの息子はひどく憂鬱な顔をするのだが、それがどこか愛嬌に思えてならなく、ついラグサット家の豪奢なディナーにお呼ばれされてしまうのであった。
夫人は、大臣が留守の間は、暇を持て余していた。彼女は、甘口の野菜スープをすすった後、艶やかな口元を輝かせて、小声で言った。
「わたくし、正直申し上げて、あのチャゴス殿下はお嫌いですわ」
誰もが抱いていることを、つい名を挙げて口走ってしまった夫人に対して、我々隣人は、いかにそれが良識者の考思であるかを力説した。何故なら、夫人が今、禁句をもらしたことがばれてはならないからである。
「わたくし、チャゴス殿下のちっちゃい目が嫌い。あんなちっちゃな目で、もし見つめられたら、わたくしどうしましょう!」
数日後、夫人の提案により、数人の料理人を従えて、サザンビーク国領西の高台付近の、とある渓谷へ、私とラグサットと夫人の三人は、オープン・カフェと称して大がかりなピクニックに出掛けたのであった。
「わたくし、小鳥が大好きだという親戚の甥っ子に、ガチャコッコの魔物をプレゼントしましたら、それはそれは喜んでいただけましたの。でもそれから1ヶ月が経ちましたでしょうか。その甥の子は、ガチャコッコの鉄で出来た羽根にやられて、額を三針縫いましたの。真っ赤な血が飛び散ったそうですわ。わたくし、もう申し訳なくてたまりませんでしたの」
ラグサットは、遠くの空を眺めては、深く溜息をついて目を閉じた。
「わたくし、お詫びのしるしに、デビルパピヨンを差し上げましたわ」
夕刻になって、どこからか、気品のある物悲しいソロギターの旋律が聞こえてきた。その旋律は岩肌にこだまして、それがとてつもなく大きな余韻を作り出していた。いったい、どこから聞こえてくるというのか。
「…あれは…ジョー・パスの弾くギター…かしら」
夫人は何の前触れもなく、小さな声でそう呟いた。ラグサットは寄り添うようにして夫人の肩に手を触れ、口を開いた。
「そうだね。ジョー・パスさ。誰かが彼のレコードをかけているんだ」
我々はしばし無言となり、その響き渡る余韻に集中して耳を傾けていた。
「DJANGO!」
夫人はそう叫ぶやいなや、足下をふらつかせながら岩壁の向こうへ走っていった。私は予期せぬ夫人の行動にまったく困惑した。
彼女はその鳴り響くギター・サウンドを聞いて、DJANGOと知った。だがそれがなんだというのか。
「あの曲は、母の若き頃の思い出というのか、
若き頃に愛した人を思い出したのでしょう」
私はラグサットに尋ねた。
「いったいどこから聞こえてくるんだろう。まったく不思議な曲だけれど」
「あれは夜の帝王が眠るために聞いているんだよ。あれは不思議な魔物でね。一種のジプシー集団みたいなもので、ジョー・パスの曲を愛しているのさ」
私はこの見渡す限りの世界の、漆黒の闇に佇む恐ろしさを知ったような気がした。
〈了〉