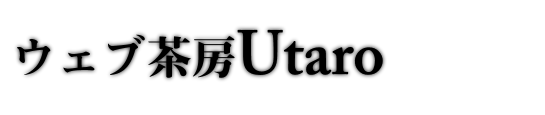![]()
自分にどんな動機があってそこに行ったのかは覚えていない。とにかくそこは、東京の簿記専門学校の校内であった。
第一幕。
その日、卒業した高校の同窓会があるとかで、私はその時間に間に合うように、学生服を用意していた。というのは、その前に私は高校の門の所まで来た時に、集まっている同窓生全員が学生服を来ていたために、恥ずかしくなって私はその足で逃げて帰ってきたのだ。
一旦戻った私は、専門学校の授業がこれからあるというのに、学生服を持って、同窓会に出席しようという企みでいた。
それ以上に、私は、在籍中の専門学校を中途退学しようという気になっていた。もともと入学金も納めないで紛れ込んだ専門学校なのだから、ちっとも残念ではなかった。
他の生徒たちは授業のために、別の教室に移動し始めていた。誰かが、私の学生服を持っている姿に気づいてこっちを見たが、私にとってはまったく知らない人間で、口も聞いたこともない学生であった。もちろん向こうも私が誰かなど知っているわけでもなく、お互いに初めて出会った人間ばかりで、関心はなかった。
私はその場を去り、学校の校庭を歩いていった。たいへん広い校庭で、植木が多く、歩いているだけで気持ちが良かった。空は晴れていて雲もなく、青い空だけが目に焼き付いた。その下の照らされた木々の表情の豊かさには心がどよめいた。そして木々を揺らしている少しばかりの暖かい風が、私に向かって別れのあいさつをしているようで、何だか悲しくなるのだった。
校庭を抜けると、そこは都会の無機質な交通の断片があった。
第二幕。
私は修学旅行に来ているようだった。しかもそこは、日本ではなく、どうやらアメリカのブロードウェイであった。
だが、一般的にイメージするブロードウェイの光景ではなかった。建物の上に“ブロードウェイ”と書かれてあるだけで、何か模造された建物の集落のようだった。
そこらの人間のうち、日本人は私一人だった。ときに第一幕の残存があるようで、校庭の中で遊んでいる外人の生徒がいたりもして、ますますそこがどこだか、私は何をしに来ているのか、さっぱりわからなくなっていた。
だが最終的に、模造された集落の町にいることが確認できた。私はその町を一人で歩くことにした。
歩きにくかった。町中に外人が密集していて、何やら拳銃を撃って遊んでいるのだった。
拳銃を撃っているといっても、私には緊迫した雰囲気には見えず、やはり遊んでいるのだった。だが容易にそこを通り抜けることはできず、なかなか歩くことができないでいた。そのために私は遠回りをしながら、町の全貌を見ようと少しずつ歩いてみることにした。
光景の果てには、海が見える。潮の香りと波の音がかすかに聞こえる。どうやら、丘の上の町という様子であった。
歩くと次第に、同年代の日本人が戯れていることに気づいた。やはり修学旅行なのか。
ふと見ると、私の通りすぎた喫茶店の中に、中学校時代の親友と、その恋人らしき女性がクリームソーダを飲んでいる。二人は会話もせずにクリームソーダに口を付けている。だが明らかに恋人という雰囲気だった。
私はその親友だった彼が、その女性と二人きりでいることにショックを感じていた。私の孤独に愛着を感じていたのは、彼がいつになっても彼のままで、どこか寂しげで悲しい姿のままであることに確信を持っていたからで、その確信が崩れたとなると、ますます私の孤独が現実的なものとなり、今度は本当の意味での孤独を感じ、彼らへの嫉妬を遥かに通り越した「友情の絆」の切断が、私を襲うのだった。
その後私は、眠りに就くために、人が入れるくらいのカプセルに入れられ、人間の体液にも似た液体の中に漬かり、目を閉じるのだった。
口の中に僅かながらの液体が入り、苦しむことなく眠ることができたのは、彼らが私の目の前に現われたことが好い結果となったのかもしれない。その深い眠りは、私の死にも似ていたが、私の大いなる復活の序曲であるような気がしてならなかった。
〈了〉
(1995-1997)